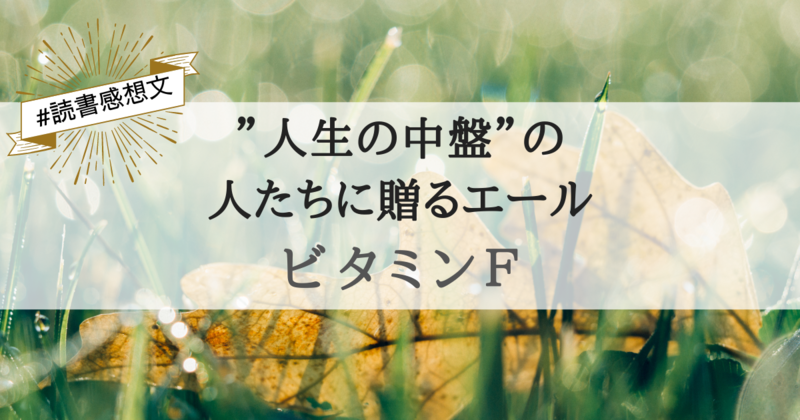
第124回(2000年)直木賞受賞作です。
2002年にNHKBSにてドラマ化もされたそうです。 (Wikipediaでキャストを見てみましたが、原作のイメージに合うキャストだと思いました。)
ビタミンF 感想
「炭水化物やタンパク質やカルシウムのような小説があるのなら、ひとの心にビタミンのようにはたらく小説があったっていい。」という思いが込められた短編集です。
Family(家族)、Father(父親)、Friend(友達)、Fight(戦う)、Fragile(脆い)、Fortune(運)...「F」がキーワードの7つの家族の物語です。
文庫帯の「涙腺キラー・重松清の最泣の一冊 100%涙腺崩壊!」が目に入り、書店で手に取りました。
そして1話目の物語を読み終えた私は...「まずい、チョイスを間違えたかもしれない」と思うのです。
そして4話目を読み終わって「もう読むのやめようかな...」と思うのです。
舞台は2000年くらい、そして主人公もアラフォー。
その時代のことは知っている、そして主人公は今の私と同年代...感情移入できる材料は揃っているはずなのに、全くできない。
いや、むしろちょっとだけイラっとする。
なぜだ?
100%涙腺崩壊!と書かれているのに私は泣けないどころか、なぜイラっとしているのだ?
心を落ち着けるために、Amazonのレビューをちょっとだけ覗く。
全体評価★4つ。
うそうそ、みんな高評価じゃん!と余計パニックに陥るのでした。
とりあえず、最後まで読もうと5話目「なぎさホテルにて」を読み始め...
見事にバズーカーで胸を撃ち抜かれていたのでありました。
そして、私は気づくのです。
なぜ、前半の物語でイラっとしたか。
全ての主人公は40歳前後の父親なのですが、私は前半のお話を同年代であるはずの親目線ではなく「子供の立場」で読んでいたのです。
だからこそ...悪あがきするような、自分の正義を振りかざすような父親の姿に思春期の子供目線である私はイラついたわけです。
しかし、5話目「なぎさホテルにて」で急に私は妻(母親)の立場になりました。
夫婦仲が悪くなり、家族が壊れてしまいそうな状況が描かれているのですが...それが6年程前の自分に重なり、胸が苦しくなりました。
主人公の父親は、特に不満もない平凡な日常の中で不意に「俺の人生は、これか ー。」と思い、妻に冷たく接します。
「わたし、なにかあなたの気に入らないようなことした?」と時に涙ながらに何度も聞く妻に「直す、直さない、好き、嫌いとかじゃない」みたいなことを言います。
妻が悪いわけでもない、妻が嫌いになったわけでもない、これというきっかけがあったわけでもないが、妻に嫌悪感を感じる主人公の男。
重松清は、我が家の話を書いたのか?
これは、6年前のうちの夫の話なのか?と思うほどでした。
ということは、割とよくある話...というかアラフォー男にとって、こういう気持ちや状況になることは珍しいことではないのかな?
物語の夫婦がその後に離婚したのか、しなかったのかは分かりませんが...少し希望のある終わり方でした。(ちなみに私たち夫婦は、以前よりも夫婦円満に仲良く暮らしています。)
ほんの少しのことでズレ始め、ほんの少しのことでそっと寄り添うこともできる。
でも他人だから、結構簡単に背を向けて歩き始めることもできる。
ときめきや新鮮さと共に思いやることを失い、"普通の日常"になってしまったパートナーを鬱陶しく思う。
そんな”夫婦”と言うものを何とも生々しく書いている作品でした。
この「なぎさホテルにて」を含む後半3話は、心地よく読むことが出来ました。
そして最後まで読んで気づくのです。
まんまと重松清ワールドに引きずり込まれたな、と。
前半4話で私がイラっとしたのも、後半3話を心地よく読めたのも...描かれているのが、ただ普通のごくありふれた日常。
だからこそ、自分が様々な立場に立ち、気づけば物語の中に入り込んでいました。
家族や夫婦がキラキラして愛おしいばかりの存在から、”あたりまえ”になり時に億劫にさえ感じてしまう。そしてもう自分がそんなに若くないことを実感する...
この本はきっと、そんな人生の中盤に差し掛かかった人たちへのエール。
「がんばれ」なんて一言も書いていないけれど、「あなただけじゃない」というエールなんだと思います。(#重松清)



